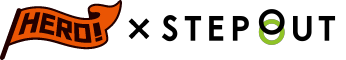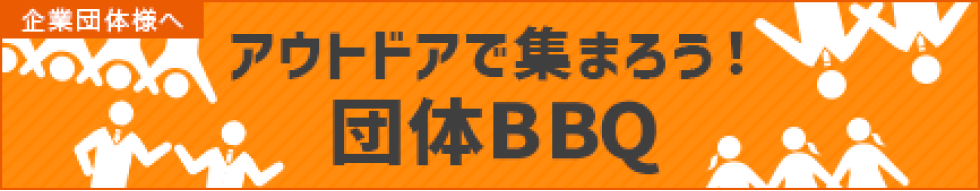2024.11.06
焚火のポイント ~炎の調節と維持の仕方~
先日話の続きになりますが、本日も焚火の話を少し。
前回は焚火をする前のお話をさせて頂きました。
今回は焚火をしている最中のお話となります。
当店の薪を使うと、針葉樹で約2~3時間、広葉樹で4~5時間ほどの燃焼時間と
お話を致しましたが、この時間には薪の組み方や扱い方が大きくかかわってきます。
例えば、着火の際こんな薪の組み方をされる方もいると思います。
漢字の【井】に似てるので、"井形に組む"なんてよく耳にすると思います。
確かに燃やし始めが肝心なので、その際には適した組み方ではあるのですが
そのあとも同じ組み方だとキャンプファイヤーになります。
この状態では1時間とせずに薪は全て燃え尽きてしまうでしょう。
火を管理するときに意識するのは、空気の流れと薪の距離です。
薪をあまりにもたくさん入れてしまうと、薪がうまく燃焼しない場合があります。
その場合は大量の煙が上がってきます。
不完全燃焼を起こして煙が上がってしまっているので、薪の量を減らしたり
組み方を変えて空気が中に通るように変えてみましょう。
火が収まり、炭が煌煌と赤く光る状態が"熾火"です。
一番火が安定している状態になるので、料理に適しています。
安定はしているのですが何もしないと、当然このまま消えてしまいます。
火を起こすためには熱が必要になります。
新しく入れた薪に着火したいとき、火力を出したい場合は熾火を近づけて熱を集めてください。
逆に焚火を長持ちさせたい場合は、薪同士の距離を少し離して熱を分散させてください。
後は安全に行うためにも風向きには十分注意をしてください。
風下にテントや体を置くと、火傷や衣類に穴が開く可能性があります。
安全に余裕をもって焚火を楽しんでくださいね。